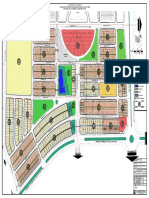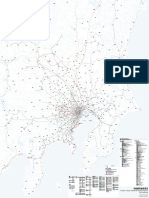Professional Documents
Culture Documents
P knj2021
P knj2021
Uploaded by
Taniya GhoshCopyright:
Available Formats
You might also like
- 心理学研究「投稿の手引き」2015Document80 pages心理学研究「投稿の手引き」2015qq1309782250No ratings yet
- UntitledDocument136 pagesUntitledPamela LuevanoNo ratings yet
- 030-F-Cortadora RadialDocument1 page030-F-Cortadora RadialFernandoNo ratings yet
- 令和2年4月号Document19 pages令和2年4月号nhồi thịt Bánh baoNo ratings yet
- Yasukuni Shiori JaDocument2 pagesYasukuni Shiori Ja咲畑梨深No ratings yet
- BSJ 15 May 2021Document8 pagesBSJ 15 May 2021Silvia Regina AlvesNo ratings yet
- Kanji n3Document10 pagesKanji n3Lý PhạmNo ratings yet
- 31Document322 pages31Asmaa SayedNo ratings yet
- Bản Đồ Phân Lô A0 - MớiDocument1 pageBản Đồ Phân Lô A0 - MớiThanh VlogNo ratings yet
- MAML - Volume 9 - Issue 1 - Pages 706-726Document19 pagesMAML - Volume 9 - Issue 1 - Pages 706-726Abdo SadokiNo ratings yet
- 【教室入り】2022前期日本語クラス時間割Document1 page【教室入り】2022前期日本語クラス時間割Aysu İmran ErkoçNo ratings yet
- 85 NoajDocument40 pages85 Noajחיים יפהNo ratings yet
- 006 F Hse Epp DiarioDocument1 page006 F Hse Epp DiarioFernandoNo ratings yet
- To But J StationDocument1 pageTo But J Stationsae.tanahashi333No ratings yet
- UntitledDocument33 pagesUntitledPamela LuevanoNo ratings yet
- IF 2 - 8 MarruaDocument2 pagesIF 2 - 8 MarruaTuấn TrungNo ratings yet
- DbenghoumariDocument376 pagesDbenghoumarivideo &musicNo ratings yet
- 93 MiketzDocument32 pages93 MiketzWXSNo ratings yet
- Banghay-Aralin Sa Filipino 6 COTDocument3 pagesBanghay-Aralin Sa Filipino 6 COTArmelou MagsipocNo ratings yet
- Calendarios 2022 - 2023Document3 pagesCalendarios 2022 - 2023Aldo david Oviedo lopezNo ratings yet
- Bagi Jurus Rawat Luka Kaki PDFDocument10 pagesBagi Jurus Rawat Luka Kaki PDFDian Noviandini MuharramNo ratings yet
- MAML - Volume 7 - Issue 2 - Pages 139-162Document24 pagesMAML - Volume 7 - Issue 2 - Pages 139-162zahirabena7No ratings yet
- BunkuzuDocument1 pageBunkuzutbky27914No ratings yet
- 29 01 2023 Pero El Señor Estuvo A Mi Lado y Me Dio Fuerzas PR JavierDocument5 pages29 01 2023 Pero El Señor Estuvo A Mi Lado y Me Dio Fuerzas PR JavierhugomartzNo ratings yet
- Teatrul Noh2Document17 pagesTeatrul Noh2Cozmina Denisa ScorobeteNo ratings yet
- Mendapatkan CintaDocument58 pagesMendapatkan Cintavaldo mortNo ratings yet
- دليل إعداد التصاميم - مجال التشجير والحدائق العامة 1435هـDocument65 pagesدليل إعداد التصاميم - مجال التشجير والحدائق العامة 1435هـlujainNo ratings yet
- Wsew JP 19 Map Tokyo 0222 PDFDocument1 pageWsew JP 19 Map Tokyo 0222 PDFhextobinaryNo ratings yet
- Geología Y Vino: en ZamoraDocument185 pagesGeología Y Vino: en ZamoraCarlos AsenjoNo ratings yet
- 90 VayetzéDocument32 pages90 VayetzéWXSNo ratings yet
- The Weather in Britain 64Document1 pageThe Weather in Britain 64ibolya.dr.gottnekne.dr.kunNo ratings yet
- Extraño RelojDocument3 pagesExtraño RelojYina VegaNo ratings yet
- 思想起(音樂比賽版)(總譜及分譜)Document40 pages思想起(音樂比賽版)(總譜及分譜)Liang ZhangNo ratings yet
- 金田弘 (1985.5) 「なかった」考 PDFDocument7 pages金田弘 (1985.5) 「なかった」考 PDFNomura YoshikiNo ratings yet
- Tabla de Referencia A 106 BDocument1 pageTabla de Referencia A 106 BJose Guadalupe DomínguezNo ratings yet
- Article 157718Document33 pagesArticle 157718inourimeriemNo ratings yet
- JR MapDocument1 pageJR Map95pzfmx47nNo ratings yet
- 22 01 2023 Sirvamos Hasta El Fin Esperando Nuestro Galardon PR JavierDocument6 pages22 01 2023 Sirvamos Hasta El Fin Esperando Nuestro Galardon PR JavierhugomartzNo ratings yet
- Seoul Rosenzu 01Document1 pageSeoul Rosenzu 01bxjh9ftqfhNo ratings yet
- Conto Escola Assis 2edDocument10 pagesConto Escola Assis 2edFabricio GuimaraesNo ratings yet
- Topic 3 Ethical and Legal Implications of PracticeDocument7 pagesTopic 3 Ethical and Legal Implications of Practicemarc gorospeNo ratings yet
- TH M His Ar 2015 49Document60 pagesTH M His Ar 2015 49ali ali39No ratings yet
- 19 02 2023 Yo Soy La Puerta PR JavierDocument5 pages19 02 2023 Yo Soy La Puerta PR JavierhugomartzNo ratings yet
- Carnival of Rust PDFDocument4 pagesCarnival of Rust PDFzatanna10No ratings yet
- القمحDocument2 pagesالقمحJOE SAADNo ratings yet
- 11 02 2024 No Busques Nada Fuera de DiosDocument5 pages11 02 2024 No Busques Nada Fuera de DiosJoel Antonio Menendez HernandezNo ratings yet
- PNL y Coaching Ontologico Nivel 1Document66 pagesPNL y Coaching Ontologico Nivel 1ricardoNo ratings yet
- 関西学院大学Document36 pages関西学院大学liq55667No ratings yet
- Reading Practice 2 Japanese StudyDocument6 pagesReading Practice 2 Japanese StudyDavid McCartney100% (1)
- MAML - Volume 5 - Issue 1 - Pages 405-433Document28 pagesMAML - Volume 5 - Issue 1 - Pages 405-433tamershahd06No ratings yet
- 4PM0 01 Que 20150119Document32 pages4PM0 01 Que 20150119munzarinNo ratings yet
- 19 03 2023 Yo Soy La Vid PR Javiier CDocument5 pages19 03 2023 Yo Soy La Vid PR Javiier ChugomartzNo ratings yet
- Vivir Mi Vida Trombone 2 - CompressDocument2 pagesVivir Mi Vida Trombone 2 - CompressSantiago AlbaNo ratings yet
- Wakefield 1Document3 pagesWakefield 1JRaoneNo ratings yet
- Por Que Te Quiero - Bajo Eléctrico (Los Ángeles Negros)Document1 pagePor Que Te Quiero - Bajo Eléctrico (Los Ángeles Negros)Luis FernandoNo ratings yet
- 新美南吉童话中的战争意识Document46 pages新美南吉童话中的战争意识Kai Liang KeeNo ratings yet
- MAML Volume 8 Issue 3 Pages 379-402Document23 pagesMAML Volume 8 Issue 3 Pages 379-402ghadatarek735No ratings yet
- 路線図 v1.21 (201010) JPDocument1 page路線図 v1.21 (201010) JPWazzupWorldNo ratings yet
- Unit 2 T V NGDocument260 pagesUnit 2 T V NGBảo QuốcNo ratings yet
- Kotoba Marugoto 2Document52 pagesKotoba Marugoto 2kikiNo ratings yet
- Kotoba Level N5: 日本語 Romaji Indonesia 動詞 (どうし) Kata KerjaDocument6 pagesKotoba Level N5: 日本語 Romaji Indonesia 動詞 (どうし) Kata Kerjareza fauzanNo ratings yet
- DownDocument90 pagesDownAl aeNo ratings yet
P knj2021
P knj2021
Uploaded by
Taniya GhoshOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
P knj2021
P knj2021
Uploaded by
Taniya GhoshCopyright:
Available Formats
Knowing fish from its name in Kanji (Chinese character)
漢字でわかる魚のかんじ
し ほ う うみ かこ しまぐに やく しゅるい さかな せいそく
日本は四方を海で囲まれた島国であり、約3700種類の魚が生息しています。
ぎょかいるい しょくぶんか か そんざい ぎょぎょう ようしょく ぎょう だ い じ さんぎょう
Japan, an island country surrounded by water on all four sides, is inhabited by approximately 3,700 species of fish.
魚介類は日本の食文化に欠かせない存在であるため、漁業や養殖業はとても大事な産業です。 ぎょかいるい すがた せいたい な ま え か ん じ し
Since the fish and shellfish make an indispensable part of the Japanese food culture, fishing and aquaculture are highly important industries there.
な ま え
その魚介類がどのような姿や生態なのかは、名前や漢字で知ることができます。
か ん じ な た ゆ ら い せつ した せつ しょうかい
The appearance and biology of fishes can be known by looking at their names in kanji (or Chinese character. The same applies below) .
名前や漢字の成り立ちの由来はいくつか説がありますが、その中でも親しみやすい説をご紹介します。 Among the different versions about the origins of Fish names in kanji, the most common accepted explanations are shown in the table below.
さめ
-SAME-
"Shark"
鮫 うなぎ
-UNAGI-
"Eel"
鰻 はも
-HAMO-
"Pike conger"
鱧 あなご
-ANAGO-
"Conger eel"
穴子 いわし
-IWASHI-
"Sardine"
鰯 にしん
-NISHIN-
"Herring"
鯡 カズノコ
このしろ
-KONOSHIRO-
"Gizzard shad"
鮗 あゆ
-AYU-
"Sweetfish"
鮎 わかさぎ
-WAKASAGI-
"Pond smelt"
公魚
ヨシキリザメ[メジロザメ目メジロザメ科] 旬:特になし ニホンウナギ[ウナギ目ウナギ科] 旬:冬 ハモ[ウナギ目ハモ科] 旬:夏 マアナゴ[ウナギ目アナゴ科] 旬:夏 マイワシ[ニシン目ニシン科] 旬:秋 ニシン[ニシン目ニシン科] 旬:春 コノシロ[ニシン目ニシン科] 旬:冬 アユ[キュウリウオ目キュウリウオ科] 旬:夏 ワカサギ[キュウリウオ目キュウリウオ科] 旬:冬
からだ およ ほそなが たいけい なが せいめいりょく つよ ゆた えいよう ゆた あな く あ な ご し ほか さかな えさ え ど じ だ い まつまえはん ほっかいどう ねんぐ こめ ふゆ しゅん じ き ふゆ このしろ か こ だ い じんぐうこうごう いくさ か うらな こ じ え ど じ だ い とくがわけ だい め しょうぐん く ぼ う さ ま けんじょう
漢字 体をくねらせて泳ぐため、つくりはねじれる・クネクネするとい 漢字 ニョロニョロと細長い体形から、つくりはズルズルと長いという 漢字 「生命力が強い
(豊か)
」であり
「栄養が豊か」
であることから、つ 漢字 穴の中で暮らしていることから
「穴子」
となった。 漢字 水からあげるとすぐ死んでしまうことや、他の魚の餌になりや 漢字 江戸時代の松前藩
(北海道)
では、年貢は米ではなくニシンであった。 漢字 冬が旬の時期なので、つくりは
「冬」
となった。
「鰶」
とも書く。 漢字 古代、神功皇后が戦に勝てるかどうかアユで占った故事にちな 漢字 江戸時代に徳川家11代目将軍
(公方様)
にワカサギが献上さ
い み こもごも い み なが ゆたか す し あ な ご に よ あま つ た よわい こめ あら あら にしん か せいちょう よ か うらない きみ
う意味の
「交」
となった。 意味の
「曼」
となった。 くりは
「豊」
となった。 メモ寿司では穴子を煮て 「ツメ」と呼ばれる甘いタレを付けて食べ すいことから、つくりは
「弱」
となった。 「米に非ず
(ではない)
」ということで、つくりは
「非」
となった。
「鰊」
とも書く。 メモ 成長するにつれて呼び名が変わり、シンコ→コハダ→ナカズミ んで、つくりは
「占」
となった。 れたことから、
「公」
があてられた。
ほね すべ なんこつ なんこつぎょるい み てんねん しゅん ふゆ え ど じ だ い ひらがげんない ど よ う うし かんさい ていばん さかな かた こ ぼ ね ほね ぎ ち ぎ ょ よ せいしょく み そ し る りょうり だ し つか に ぼ おも りょうり き い ろ たまご よ なか ぎん いろ ひか さかな けいそうるい た み うみ せいちょう さんらん みずうみ
メモサメやエイは骨が全て軟骨の「軟骨魚類」
である。サメの身は、 天然ものの旬は冬だが、江戸時代に平賀源内が
メモ 「土用の丑 の メモ 関西では定番の魚である。硬い小骨がたくさんあるので 「骨切 る。アナゴの稚魚は 「ノレソレ」
や「ハナタレ」などと呼ばれ、生食され メモ味噌汁など日本料理の出汁に使われる
「煮干し」
は、主にカタク メモ お 正 月 の お せ ち 料 理 の 黄 色 い カズノコ は ニ シン の 卵 。 →コノシロと呼ばれる。コノシロなどお腹 が銀 色に光って見える魚 メモ アユは石についたコケ (珪藻類)
を食べるため、身からキュウリ メモ 川で生まれて海で成長してまた川に上り産卵するものと、湖に
かまぼこ げんりょう た ていあん なつ た かわ こま き し ょ り おこな に ほ しそんはんえい ねが た す し ひか もの よ にお りくふう こお みずうみ おこな あ な づ ふゆ ふうぶつ
はんぺんや蒲鉾の原料になっている。 日にウナギを食べよう」
と提案し、夏に食べることが人気になった。 り」
という皮を切らないように細かい切りこみを入れる処理を行う。 ている。 チイワシを煮て干したものである。 子孫繁栄を願って食べる。 は、寿司ネタでは
「光り物」
と呼ばれる。 やスイカのようなコケの匂いがする。 陸封されたものがいる。凍った湖で行う 「穴釣り」 は冬の風物。
Shark twist their bodies as they swim, hence the use of the radical "交" meaning Eel have elongate body, hence the use of the radical "曼" meaning "long" for the Pike conger represent richness in vitality and have abundant in nutrition, hence the Conger eel live in a hall, hence the use of the character "穴 (hole)" for the name in Sardine perish fast when fished out of water and are prone to being fed on by other In the past rice was offered as a tribute to the lords in Japan. In certain regions with Season of gizzard shad are in winter, hence the use of the radical "冬 (winter)" for A very long time ago the emperors relied on sweetfish to predict the result in a Pond smelt were used as offerings to the Shogun during the Edo period of
柳葉魚 鮭 鱒 鱈 鮟鱇 秋刀魚 鱸 甘鯛 鯵
"twist" for the name in kanji. Shark and ray are "cartilaginous fishes". Shark meat name in kanji. use of the radical "豊 (abundance)" for the name in kanji. kanji. fish, hence the use of the radical "弱 (weak)" for the name in kanji. bountiful herring catches, however, herrings were offered instead of rice, hence the the name in kanji. Gizzard shad are called differently as they grow. They are called battle, hence the use of the radical "占 (fortune)" for the name in kanji. Since they Japanese history, hence the use of the character "公", meaning the "Shogun", in
is used as an ingredient in the Japanese foods known as "hampen" (pounded fish In Japan, eel is a popular delicacy in the hot midsummer (the dog days of the With numerous hard and small bones, they need a process so called "bone cutting" When served as sushi, they are pre-boiled and then are coated with a sweet sauce Niboshi, which are used in miso soup and other forms of broth in Japanese food, use of the radical "非 (not)", as "not rice", for the name in kanji. There is a tradition "Shinko", "Kohada", "Nakazumi",and later "Konoshiro". In sushi context, they fall feed on moss, they smell somewhat like cucumber. their kanji.
cake) and "kamaboko" (boiled fish paste). summer). before cooked. called "Tsume". are anchovies that are pre-boiled and dried. in Japan to eat Kazunoko, or herring roes, on the new year's day. in a group so-called "HIKARIMONO (silver-skinned fish)". "Ice fishing for pond smelt" on a frozen lake is a traditional winter sight in Japan.
ししゃも さけ にじます たら あんこう さんま すずき あまだい あじ
-SHISHAMO- -SAKE- -NIJIMASU- -TARA- -ANKO- -SAMMA- -SUZUKI- -AMADAI- -AJI-
"Smelt" "Salmon" "Trout" Cod "Angler fish" "Pacific Saury" "Sea bass" "Tilefish" "Horse mackerel"
あき さけ ときしらず
ときしらず
シシャモ[キュウリウオ目キュウリウオ科] 旬:秋∼冬 サケ[サケ目サケ科] 旬:秋鮭は秋、時鮭は春∼初夏 ニジマス[サケ目サケ科] 旬:養殖は通年 マダラ[タラ目タラ科] 旬:冬 アンコウ[アンコウ目アンコウ科] 旬:冬 サンマ[ダツ目サンマ科] 旬:秋 スズキ[スズキ目スズキ科] 旬:夏 アカアマダイ[スズキ目キツネアマダイ科] 旬:秋 マアジ[スズキ目アジ科] 旬:夏
な ま え ご やなぎ は い み ゆ ら い さんかく かたち よ い み けい じょうひん かたち よ すがた ほそなが さけつぼ かたち かっこう ふゆ ふ ぶ き ころ と ゆき とくちょう あき しゅん じ き ほそなが ぎんいろ すがた かたな くろ はんてんもよう すがた くろ い み ろ あじ あ ま み あまだい よこがお あま うみ む あつ およ
漢字 名前がアイヌ語のsusam
(susu=柳、ham=葉の意味)
に由来 漢字 つくりは三 角にとがって、形 が良 いという意 味である
「圭 」
と 漢字 上品で形の良い姿から、つくりは細長い酒壺の形をした、格好 漢字 冬の吹雪のある頃によく獲れることから、
つくりは
「雪」
となった。 漢字 あごの特徴をとらえてアンゴ→アンゴウ→アンコウとなった。 漢字 秋が旬の時期であることと、細長く銀色の姿から刀に見立て、 漢字 黒い斑点模様のある姿から、つくりは黒いという意味の
「盧」
と 漢字 味に甘味があることから
「甘鯛」
となった。また、横顔が尼さん 漢字 アジは海を群れで集まって泳ぐことから、つくりはたくさん入り
し し ゃ も い み そん み せいそう し ら こ び み ち ほう お ん よ アン コウ か ん じ つく あき かたな さかな に あま だい よ ま い み さん
することから、
「柳葉魚」
となった。 なった。 がよいことを意味する
「尊」
となった。 メモ タラは身だけでなく、精巣の
「白子」
も美味で、地方によっては 「あん」
「こう」
と音読みする
「安「
」康」
をつけて漢字が作られた。 「秋「
」刀「
」魚」
があてられた。 なった。 に似ていることから
「尼鯛」
とも呼ばれた。 混じるという意味の
「参」
となった。
ほっかいどう たいへいよう えんがん せいそく こ ゆ う う うみ た そだ せいちょう ふるさと めい じ き きた いにゅう げんざい か く ち よ らんそう み きも い かわ らんそう ど う ぐ よ あま いぶくろ ちょう みじか た み ず あ よ か しゅっせうお かんとう かんさい よ な か ま かたち よ じょう
メモホンシシャモは北海道の太平洋沿岸のみ生息する日本の固有 川で産まれて海でエサを食べて育ち、成長すると故郷の川へ
メモ メモ ニジマスは明治期に北アメリカから移入した。現在、日本各地で 「だだみ」
「たち」と呼ばれる。スケトウダラの卵 巣はおにぎりやスパ メモ 身、肝、胃、皮、えら、ひれ、卵巣は
「7つ道具」
と呼ばれ、余すこと メモ胃袋がなくて腸が短いため、フンが溜まらない。そのため水揚 メモ 成長するにつれて呼び名が変わっていく「出世魚」
であり、関東 メモ 関西では
「グジ」
と呼ばれる。タイの仲間ではないが、形や赤い メモアジには 「ゼンゴ
(ゼイゴとも呼ばれる) 」
というトゲ状のウロコ
しゅ た き か い おお べっしゅ もど さんらん たまご ご たまご い み よ ようしょく さか おこな ひんしゅかいりょう たんじょう ぐ に ん き た りょうり ないぞう いた ないぞう お い た さかな よ たいしょく に な ま え たい いっしゅ お ちか ちゅうい りょうり
種であるが、食べる機会が多いのは別種のカラフトシシャモである。 戻って産卵する。卵は 「イクラ」
(ロシア語で卵の意味) と呼ばれる。 養殖が盛んに行われ、品種改良したブランドサーモンが誕生している。 ゲッティの具として人気の 「たらこ」
として食べられている。 なく料理されている。 げされたあとも内臓が傷みにくく、内臓ごと美味しく食べられる魚。 ではコッパ→ハクラ→セイゴ→フッコ→スズキと呼ばれている。 体色が似ていることから名前にタイがつく 「あやかり鯛」 の一種。 が尾びれの近くにあるので、注意して料理しよう。
The name of smelt in Japanese originates from the Ainu word "susam", a combina- Salmon have triangular, pointed part and are well-shaped, hence the use of radical Trout look elegant and are well-shaped, hence the use of the radical "尊" meaning Cod are caught well in winter at the time of blizzards, hence the use of the radical With a marked shape of the jaw ("ago" in Japanese), the name of angler fish has Season of pacific saury is autumn and saury are likened to be a knife for its Sea bass sport a black-spotted pattern, hence the use of a radical "盧" meaning Tilefish have a sweetness to their flavor, hence the use of radical "甘(sweet)" for Horse mackerel congregate and school in the water, hence the use of the radical "
参", meaning "co-mingling of many things", for the name in kanji.
鰤 間八 鯛 太刀魚 鮪 鰹 鰆
tion of "susu" or"柳 (willow tree)" and "ham" or "葉 (leaf)", hence the use of the "圭" representing these features for the name in kanji. "good-looking" for the name in kanji . "雪 (snow)" for the name in kanji. evolved from "ango", angou", and to "anko". elongate and silver-colored body, hence the use of three characters, "秋 (autumn)", "black" for the name in kanji. their name in kanji. They are also called "nun fish" due to their profile being
two characters for the name in kanji. "Honshishamo" is a species of smelt which is In Japan, salmon roes are consumed and are called "ikura," which comes from a They are cultured in abundance across Japan, resulting in the creation of brand Their roe and testicles as well as the meat are also enjoyed as delicacy. The so-called "seven tools of the angler fish", namely the meat, liver, stomach, "刀 (knife)" and "魚 (fish)" for the name. Sea bass are called by different names as they grow, and in Kanto region, they are reminiscent of a nun. A high-end fish, tilefish are also called as "guji" in Western Having spike-shaped scales at the caudal fin, they require attention when cooked.
endemic to Japan that inhabits only in the Pacific coast of Hokkaido. Russian word for "roe". salmon. skin, gills, fins and ovaries, are all relished. The pacific saury can be savored, organs and all. called "Koopa", "Hakura", "Seigo", "Fukko" and Suzuki later as they grow. regions of Japan.
ぶり かんぱち たい はたはた たちうお さば まぐろ かつお さわら
-BURI- -KAMPACHI- -TAI- -HATAHATA- -TACHIUO- -SABA- -MAGURO- -KATSUO- -SAWARA-
"Yellowtail" "Greater amberjack" "Sea bream" "Sailfin Sandfish" "Cutlass fish" "Mackerel" "Tuna" "Skipjack tuna" "Spanish mackerel"
ブリコ
※写真は未成魚
ブリ[スズキ目アジ科] 旬:冬 カンパチ[スズキ目アジ科] 旬:夏 マダイ[スズキ目タイ科] 旬:春 ハタハタ[スズキ目ハタハタ科] 旬:冬 タチウオ[スズキ目タチウオ科] 旬:夏 マサバ[スズキ目サバ科] 旬:冬 クロマグロ[スズキ目サバ科] 旬:冬 カツオ[スズキ目サバ科] 旬:春と秋 サワラ[スズキ目サバ科] 旬:春
ふゆ しゅん じ き し わ す きゅうれき し りょうめ あいだ おびじょう も よ う いちぞく さち ゆ わた い み こ ぜ ん ぶ かいえんがん ふゆ かみなり な じ き と かみなり なが の ぎんいろ ひか た ち すがた た ち う お せ な か きゅうじたい あお ひろ は ん い かこ およ むかし さ し み た かんそう かた た はる しゅん じ き はる せ と な い か い
漢字 冬が旬の時期なので、つくりは師走
(旧暦の12月)
の「師」
となった。 漢字 上から見ると両目の間に八の字の帯状の模様が入っているこ 漢字 つくりは一族に幸を行き渡らせるという意味を込めて、全部に 漢字 日本海沿岸で冬の雷が鳴る時期に獲れるため、つくりは
「雷」
と 漢字 長く伸びた銀色に光る太刀のような姿から、
「太刀魚」
となった。 漢字 背中が青いから、つくりは
「青」
の旧字体である
「靑」
となった。 漢字 マグロは広い範囲を大きく囲むように泳ぐことから、つくりは 漢字 昔は刺身では食べず、乾燥させた堅いカツオを食べていたこと 漢字 春が旬の時期なので、つくりは
「春」
となった。瀬戸内海などで
せいちょう よ か しゅっせうお かんとう あいだ せいぎょ も よ う うす ゆ わた い み あまね おお かみなり な こ ご い はたはた か およ し たちうお い せ な か さかな あおざかな よ あたま ひろ は ん い かこ い み ゆう かた はる しゅん うみ かいゆう しゅん ち い き こと
メモ 成長するにつれて呼び名が変わる
「出世魚」
であり、関東では とから
「間の八」
→カンパチとなった。成魚になると模様は薄くなる。 行き渡るという意味の
「周」
となった。または、日本の多くのところで なった。雷が鳴ることを古語で
「ハタハタ」
と言う。
「 鰰」
とも書く。 または立ち泳ぎをすることが知られており、
「立魚」
とも言われる。 メモ サバ、イワシ、サンマなど背中の青い魚は
「青魚」
と呼ばれ、頭 広い範囲を囲む意味の
「有」
となった。 から、つくりは
「堅」
となった。 は春が旬だが、サワラは海を回遊するため、旬は地域により異なる。
かんさい に あたた うみ この しゅん ぎゃく しゅうねん と しょうゆ か こ う たまご みどりいろ き い ろ ちゃいろ か はく ぎんいろ うす まく からだ はたら よ けつえき い あ か み ぶ い あじ はらまわ ぶ い あぶら しゅん ど はる し ょ か と はつ はる おとず し はる つ うお よ さいきょうみそ
モジャコ→ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ、関西ではモジャコ→ツバ 見た目はブリに似ているが、ブリより暖かい海を好み、旬も逆
メモ 周年
(一年中)
獲れることから。 メモ 「しょっつる」
という醤油に加工される。卵は緑色、黄色、茶色と メモ ウロコがなく、代わりにグアニン箔という銀色の薄い膜が体を の働きを良くする、血液をさらさらにすると言われているDHA・EPA メモ 赤身の部位はさっぱりとした味わい、腹回りのトロの部位は脂 メモ カツオには旬が2度あり、春∼初夏に獲れる 「初ガツオ」
はさっ メモ 春の訪れを知らせる 「春告げ魚」
とも呼ばれる。西京味噌につ
よ なつ ご ろ さかな いわ ごと か さんらん こと よ た ほ ご えいよう そ ほ う ふ ふく の あじ たの あじ あき と もど あぶら や さいきょうや び み
ス→ハマチ→メジロ→ブリと呼ばれる。 で夏である。 メモ 語呂あわせから
「めでタイ魚」
であり、祝い事には欠かせない。 産卵するメスごとに異なり、 「ブリコ」
と呼ばれ食べられている。 保護している。 という栄養素が豊富に含まれている。 が乗りしっとりとした味わいが楽しめる。 ぱりした味で、秋に獲れる「戻りガツオ」
は脂がのっている。 けて焼いた西京焼きが美味。
Season of Yellowtail is winter, hence the use of the radical "師", the first letter of Greater amberjack have a stripe pattern like eight in kanji between the eyes when Sea bream is a staple fish in celebratory occasions in Japan. The fish is expected Sailfin sandfish are caught in the winter when it thunders frequently, hence the use Cutlass fish have an elongate and shiny-silver body like a sword, hence the use of Mackerel have blue color back, hence the use of the radical "青 (blue)" for the Tuna encloses a broad area as they migrate, hence the use of the radical "有" In the past skipjack tuna were not eaten as sashimi, but was consumed in a dried, Spanish mackerel is in season in the spring, hence the use of the radical "春
鮃 鰈 河豚 鮑 烏賊 蛸 帆立貝 牡蠣 鯏
the old word for December, for the name in kanji. looked at from above, hence the name literally "between" and "eight" in kanji. to meet a wish to ensure happiness through the entire family, hence the use of the of radical "雷 (thunder)" for the name in kanji. the character "太刀 (long sword)" for the name in kanji. The fish are known for name in kanji. meaning hold broadly for the name in kanji. The red meat has a refreshing flavor, hardened form, hence the use of the radical"堅 (hard)" in their kanji. The "first skipjack (spring)" for the name in kanji. In Japan, it is served after being marinated in Saikyo
Yellowtail are called by different names as they grow, and in Kanto region, they are Greater amberjack are similar in appearance to yellowtail, but prefer warm sea, radical "周" meaning "broadly" for the name in kanji. The roes vary in color depending on the female that lays them. The roes are called swimming upright, hence the other name "立魚 (standing fish)". Fish with blue-colored back like mackerel and sardine are called "bluefish" and while the cut around the belly is laden with fat, giving a moist taste. tuna" caught early in the year between spring and the beginning of summer have a miso and grilled.
called "Mojako", "Wakashi", "Inada", "Warasa", and "Buri" later as they grow. and are in-season in the summer. as "buriko" and are relished. they contain abundant nutrients such as DHA and EPA. refreshing taste, while "returned skipjack tuna" caught in the autumn are laden with fat.
ひらめ かれい ふぐ あわび いか たこ ほたてがい かき あさり
-HIRAME- -KAREI- -FUGU- -AWABI- -IKA- -TAKO- -HOTATEGAI- -KAKI- -ASARI-
"Bastard halibut" "Flounder" "Blowfish" "Abalone" "Squid" "Octopus" "Scallop" "Oyster" "Short-neck clam"
ヒラメ[カレイ目ヒラメ科] 旬:冬 マガレイ[カレイ目カレイ科] 旬:夏 トラフグ[フグ目フグ科] 旬:冬 クロアワビ[古腹足上目ミミガイ科] 旬:夏 スルメイカ[ツツイカ目アカイカ科] 旬:夏 マダコ[タコ目マダコ科] 旬:夏 ホタテガイ[イタヤガイ目イタヤガイ科] 旬:春 マガキ[カキ目イタボガキ科] 旬:冬 アサリ[二枚貝綱マルスダレガイ科] 旬:春
ひら からだ なら な ま え ひ ら め からだ うす は うす ちゅうごく かわ あじ ぶたにく なか ぶた かいがら いわ み つつ とり すいめん う ぎゃく うで い み か ん じ かたほう から ほ はし しん ほ ひょうめん はげ か ん じ れい あさ あさ よ
漢字 平たい体に目が二つ並んでいることから名前は
「平目」
となり、 体が薄いことから、つくりは木の葉をイメージした薄いという
漢字 漢字 中国の河にいたフグが、味が豚肉のようにおいしく、お腹が豚 漢字貝殻が岩にくっついて、身が包まれているように見えることか 漢字鳥 が水 面に浮 かぶイカをついばもうとしたら、逆にイカが腕 漢字 八本の足をクモに見立て、アシダカグモの意 味がある漢 字 漢字 片方の殻を帆のように立てて走ると信じられていたので 「帆を立 漢字 表面がゴツゴツしているため、激しいイメージの漢字 「厲」と、 漢字 水の浅いところで貝を漁ることからアサリと呼ばれ、つくりは
か ん じ ひ と も じ ひら い み は かわ ぶた つつむ の つか ちゅうごく こ じ ゆ ら い からす ぞく たこ じっさい から かいへい ふんしゅつ いどう むかし かんが おす お ん よ り
漢字一文字ではつくりは 「平」 となった。 意味である 「 」となった。 のようにふくれていたことから
「河」 と
「豚」 があてられた。 ら、つくりは
「包」 となった。 を伸ばして捕まえてくるという中国の故事に由来して、 「烏」 と
「賊 (= 「蛸」 があてられた。 てる貝」。実際は、殻を開閉することで水を噴出して移動する。 昔はオスしかいないと考えられていたため 「牡」 があてられた。 「リ」と音読みする 「利」となった。
み わ て ま え お ば あ い む み わ かた て ま え お ば あ い む どく ちょうり ていきょう めんきょ から ひら おな ま いっしゅ こうきゅう き け ん かんこく いち ぶ かいばしら がいとうまく た くろ べつめい うみ よ えいようほうふ とく あ え ん おお しお す な ぬ ちょうり ちょくぜん
メモカレイとの見分け方は、エラを手前に置いた場合、左向きにな ヒラメとの見分け方は、エラを手前に置いた場合、右向きにな
メモ メモ テトロドトキシンという毒があるので調理・提供するには免許 メモ 殻は平たいが、サザエなどと同じ巻き貝の一種。日本では高級 危険)
」があてられた。 メモ アジアでは日本、韓国、タイ、EUではスペインやイタリアなど、一部の メモ 貝柱だけでなくヒモ(外套膜)も食べられている。ヒモにある黒 メモ 別名
「海のミルク」 と呼ばれるほど栄養豊富で、特に亜鉛が多く メモ 塩水につけて
「砂抜き」 したアサリを、調理する直前に水の中で
こざかな た は するど すな た ひつよう らんそう しお つ じゅくせい た しょくざい いわ せき た かいるい おな なんたいどうぶつ からだ かいがら な ご り くに た かんさい はんげしょう ごろ た しゅうかん てん やく こ てき に ふく あ え ん み か く せいじょう こ う か ぷんほど ま ちょうり た とき かいばしら と
るのがヒラメ。小魚を食べるため、カレイよりも口が大きく歯が鋭い。 るのがカレイ。砂の中のゴカイを食べるため、おちょぼ口である。 が必要。卵巣は塩とぬかに漬け熟成させて食べられている。 食材として祝いの席で食べられている。 メモ イカは貝類と同じ軟体動物。体の中には貝殻の名残がある。 国で食べられている。関西では半夏生 (7月頃) に、タコを食べる習慣がある。 い点は目で、 約80個あるので敵を早く見つけて逃げることができる。 含まれている。亜鉛は味覚を正常にする効果がある。 1分程かき混ぜてから調理すると、 食べる時に貝柱が取れやすくなる。
Bastard halibut have a pair of eyes lined up on their flat body, hence the use of the The body of flounder is thin like a leaf, hence the use of radical " (leaf)" and a Blowfish in the rivers in China are tasty like a pork and have plump stomach like a Abalone's shells cling to rocks, and their body seem to be wrapped up, hence the Chinese fable reads that when a bird tries to peck at a squid floating on the surface Octopus with its eight limbs are likened to a spider, hence the use of the radical " Scallop was believed to move with one of its shells standing like a sail, hence the Japanese Oyster have a rugged surface, and in the past only male oyster were considered to Short-neck clam are hunted in the shallow water, hence the Japanese name
海老 蟹 海胆 海鼠 海鞘 海苔 昆布
radical "平" meaning flat for the name in kanji. radical indicating fish, for the name in kanji. pig, hence the use of two characters "河 (river)" and "豚 (pig)" for the name in use of the radical "包 (wrap)" for the name in kanji. of the water, the squid stretches its arms to capture the bird, hence the use of two ", meaning "huntsman spider", for the name in kanji. name with two characters "帆 (sail)" and "立 (stand)" . The black dots on the mantle lobe exist, hence the use of two characters "厲", meaning "rough", and "牡", meaning "asari" meaning "search" for the name. After sand being removed in salt water,
One can tell bastard halibut from flounder by placing it with its gill on your side. The You can tell flounder from bastard halibut by placing it with its gill on your side. The kanji. Since blowfish contains a toxic substance, known as tetrodotoxin, a special In Japan, abalone is eaten as a high-end dish and is relished on celebratory characters "鳥 (bird)"and "賊 (dangerous)" for the name in kanji. The octopus is consumed in certain countries around the world, such as Japan, serve as eyes. With about 80 of them, scallop can spot predators early enough to escape "male", for the name in kanji. Oyster contain copious amounts of zinc. short-neck clams should be stirred in water for about a minute right before
former faces left. former faces right. license is required in order to prepare and serve it for consumption. occasions. Like shellfish, the squid is a mollusk. South Korea and Thailand in Asia and Spain and Italy in Europe. from them. cooking. This facilitates removing the adductor muscle at a meal.
おも か ん じ がわ い ち ぶ ぶ ん さかな か ん じ さかなへん おお
へん
に漢字の左側に位置する部分のこと。魚の漢字
主に漢字の左側に位置する部分のこと。魚の漢字は「魚偏」をつけることが多い。
主 多い。
偏
Hen A component of kanji that is predominantly located on their left-hand side. Kanji for fish names are
えび かに うに なまこ ほや のり こんぶ (Left-side radical) often found with the "fish radical (魚)" .
-EBI- -KANI- -UNI- -NAMAKO- -HOYA- -NORI- -KOMBU-
"Shrimp" "Crab" "Sea urchin" "Sea cucumber" "Sea squirt" "Laver" "Kelp" ことば せつめい おも か ん じ がわ い ち ぶ ぶ ん い もの すがた せいたい あらわ おお
つくり
言葉の説明 主に漢字の右側に位置する部分のこと。生き物の姿や生態を表していることが多い。
主に漢字の右側に位置する部分のこと。生き物の姿や生態を表していることが多い。
旁
Explanation Tsukuri A component of kanji that is predominantly located on their right-hand side. It often represents the
of terms (Right-side radical) appearance or biology of a living thing.
さかな お い じ き と りょう おお じ き ち い き こと
しゅん 魚の美味しい時期、または獲れる量が多い時期。地域により異なることがあるので、
魚 の美味しい時期、または獲れる量が多い時期。地域により異なることがあるので、
旬 じ ぶ ん す
自分の住んでいる地域ではいつが旬になるのか調べてみよう。
自分の住んでいる地域ではいつが旬になるのか調べてみよう。
ち い き しゅん し ら
Shun
(In season) The best time to taste a specific fish, or a period when the catch is high. Since the season of fish
may differ by the region, try to find the time when certain fish are in season in your area.
クルマエビ[十脚目クルマエビ科] 旬:夏 ズワイガニ[十脚目ケセンガニ科] 旬:冬 キタムラサキウニ[ホンウニ目オオバフンウニ科] 旬:夏 マナマコ[楯手目シカクナマコ科] 旬:冬 マボヤ[マボヤ目マボヤ科] 旬:夏 スサビノリ[ウシケノリ目ウシケノリ科] 旬:冬 マコンブ[コンブ目コンブ科] 旬:夏 春…spring、夏…summer、秋…autumn、冬…winter
こし ま すがた ろうじん たと か ん じ うみ おい かい ぶんかい うし かど かたな うし から せいしょくそう きも きも い み か ん じ きも よる かつどう かいてい すがた うみ かた かわ おお かたな さや うみ こけ かいそう こけ に うみ こけ ご こ ん ぶ い み はつおん な ま え ゆ ら い
漢字腰が曲がっている姿を老人に例えて、漢字は
「海」
と「老」
があて 漢字 「解」
を分解すると
「牛「
」角「
」刀」
となり、牛をバラバラにするイ 漢字 殻の中の生殖巣を胆 (=肝の意味) と見立て、漢字に「胆」
があ 漢字 夜に活動し、海底をはう姿がネズミのようであることから
「海」
と ホヤは硬い皮に覆われていることから、刀の鞘に見立てて
漢字 「海」 漢字苔ではなく海藻であるが、苔に似ているので「海」と
「苔」があてら 漢字 アイヌ語の昆布を意味する「Kompu」の発音が名前の由来と さかな し ご と かた は い ふ ひ ば い ひ ん こうかい
か ん じ こ う ら だ っ ぴ かい う に か あか きも い み ねずみ さや な ま え
ひょうめん い あ ※このポスターは魚のお仕事をしている方に配布している非売品です。ポスターのデータは HP(http://fish-jfrca.jp/)で公開中です。
られた。 メージの漢字。カニは甲羅を脱皮することから
「解」
があてられた。 てられた。
「雲丹」 とも書き、
「丹 」は肝が赤いことを意味している。 「鼠」
があてられた。 と
「鞘」
があてられた。 れた。名前は表面がぬるぬるしているから、ヌル→ノリとなった。 言われている。字は当て字とされる。 * This poster is distributed to fishery-related workers and is not for sale.
なが こし ま すがた ちょうじゅ しょうちょう あし な ま え あし た いろ ぶ ぶ ん せいしょくそう さ し み ゆ す み そ た ほ かいるい しょくぶつ びさくどうぶつ いわ ふちゃく せいかつ つか ありあけかい せ と な い か い か く ち こ ん ぶ りょうり だ し か そんざい うみ
メモ 長いヒゲと腰が曲がっている姿から、エビは長寿の象徴として メモ カニの脚は10本。タラバガニは名前にカニがつくが脚は8本し メモ 食べているオレンジ色の部分は、
ウニの生殖巣である。ウニは メモ ナマコは刺 身や茹でて酢 味噌をつけて食 べられている。干し メモ 貝類や植物ではなく尾索動物である。岩などに付着して生活し メモ おにぎりに使われているノリは、有明海や瀬戸内海など各地で メモ 昆布は日本料理の出汁に欠かせない存在。海の中にいるときは The data on the poster is available on the website of Japan Fisheries Resource Conservation Association
え ん ぎ よ しょくざい いわ ごと か な か ま おな きょくひどうぶつ ちゅうかりょうり こうきゅうしょくざい くろ よ ようせい ころ かいちゅう およ ようしょく だ し かんそう だ し
(JFRCA) (http://fish-jfrca.jp/eng/index_en.html).
縁起の良い食材とされ、お祝い事に欠かせない。 かなく、ヤドカリの仲間である。 ヒトデ、ナマコと同じく棘皮動物である。 たナマコは中華料理の高級食材で、
「黒いダイヤ」
と呼ばれる。 ているが、幼生の頃は海中をおたまじゃくしのように泳ぐ。 養殖されている。 出汁が出ないが、
乾燥させることでおいしい出汁が出るようになる。
Shrimp are likened to an elderly for curved back, hence the use of two characters A kanji "解" is broken down into three radicals, or "牛 (cow)","角 (horns)", and" The gonads inside a sea urchin's shell can be seen as a liver, hence the use of two Sea cucumber are active at night and crawls along the ocean floor like a mouse, Sea squirt are covered with hard skin and can look like a sword sheath, hence the Laver are marine algae but look like moss, hence the use of two characters"海 Kelp is pronounced "Kompu" in the Ainu language, hence the Japanese name 作製:国産水産物流通促進センター構成員 公益社団法人 日本水産資源保護協会
"海 (sea)" and "老 (old)" for the name in kanji. 刀 (knife)", and it has an image of dismembering a cow. Crab break the shell and characters "海 (sea)" and "胆 (liver)" for the name in kanji. The orange portion of hence the use of two characters "海 (sea)" and "鼠 (mouse)" for the name in kanji. use of the two characters "海(sea)" and " (sheath)" for their name in kanji . (sea)" and "苔 (moss)" for the name in kanji. The Laver used for rice balls are "kombu". Created by: Japan Fisheries Resource Conservation Association (Public interest incorporated association)
Shrimp is auspicious food as a symbol of long life, and is a must-serve upon cast it off, hence the use of the radical "解", meaning "break down" for the name sea urchin for food use is its gonad. Sea cucumber is relished as sashimi, or is boiled and served with vinegared miso. Sea squirts are neither shellfish nor plants. They belong to the Urochordata subphy- cultured all over Japan. Kelp is a must-have ingredient for broths in Japanese cooking. While kelp do not 監修:石井 元
celebratory occasions in Japan. in kanji. Crab have ten legs. lum. produce broth while they live in the sea, they produce broth only after they are dried.
You might also like
- 心理学研究「投稿の手引き」2015Document80 pages心理学研究「投稿の手引き」2015qq1309782250No ratings yet
- UntitledDocument136 pagesUntitledPamela LuevanoNo ratings yet
- 030-F-Cortadora RadialDocument1 page030-F-Cortadora RadialFernandoNo ratings yet
- 令和2年4月号Document19 pages令和2年4月号nhồi thịt Bánh baoNo ratings yet
- Yasukuni Shiori JaDocument2 pagesYasukuni Shiori Ja咲畑梨深No ratings yet
- BSJ 15 May 2021Document8 pagesBSJ 15 May 2021Silvia Regina AlvesNo ratings yet
- Kanji n3Document10 pagesKanji n3Lý PhạmNo ratings yet
- 31Document322 pages31Asmaa SayedNo ratings yet
- Bản Đồ Phân Lô A0 - MớiDocument1 pageBản Đồ Phân Lô A0 - MớiThanh VlogNo ratings yet
- MAML - Volume 9 - Issue 1 - Pages 706-726Document19 pagesMAML - Volume 9 - Issue 1 - Pages 706-726Abdo SadokiNo ratings yet
- 【教室入り】2022前期日本語クラス時間割Document1 page【教室入り】2022前期日本語クラス時間割Aysu İmran ErkoçNo ratings yet
- 85 NoajDocument40 pages85 Noajחיים יפהNo ratings yet
- 006 F Hse Epp DiarioDocument1 page006 F Hse Epp DiarioFernandoNo ratings yet
- To But J StationDocument1 pageTo But J Stationsae.tanahashi333No ratings yet
- UntitledDocument33 pagesUntitledPamela LuevanoNo ratings yet
- IF 2 - 8 MarruaDocument2 pagesIF 2 - 8 MarruaTuấn TrungNo ratings yet
- DbenghoumariDocument376 pagesDbenghoumarivideo &musicNo ratings yet
- 93 MiketzDocument32 pages93 MiketzWXSNo ratings yet
- Banghay-Aralin Sa Filipino 6 COTDocument3 pagesBanghay-Aralin Sa Filipino 6 COTArmelou MagsipocNo ratings yet
- Calendarios 2022 - 2023Document3 pagesCalendarios 2022 - 2023Aldo david Oviedo lopezNo ratings yet
- Bagi Jurus Rawat Luka Kaki PDFDocument10 pagesBagi Jurus Rawat Luka Kaki PDFDian Noviandini MuharramNo ratings yet
- MAML - Volume 7 - Issue 2 - Pages 139-162Document24 pagesMAML - Volume 7 - Issue 2 - Pages 139-162zahirabena7No ratings yet
- BunkuzuDocument1 pageBunkuzutbky27914No ratings yet
- 29 01 2023 Pero El Señor Estuvo A Mi Lado y Me Dio Fuerzas PR JavierDocument5 pages29 01 2023 Pero El Señor Estuvo A Mi Lado y Me Dio Fuerzas PR JavierhugomartzNo ratings yet
- Teatrul Noh2Document17 pagesTeatrul Noh2Cozmina Denisa ScorobeteNo ratings yet
- Mendapatkan CintaDocument58 pagesMendapatkan Cintavaldo mortNo ratings yet
- دليل إعداد التصاميم - مجال التشجير والحدائق العامة 1435هـDocument65 pagesدليل إعداد التصاميم - مجال التشجير والحدائق العامة 1435هـlujainNo ratings yet
- Wsew JP 19 Map Tokyo 0222 PDFDocument1 pageWsew JP 19 Map Tokyo 0222 PDFhextobinaryNo ratings yet
- Geología Y Vino: en ZamoraDocument185 pagesGeología Y Vino: en ZamoraCarlos AsenjoNo ratings yet
- 90 VayetzéDocument32 pages90 VayetzéWXSNo ratings yet
- The Weather in Britain 64Document1 pageThe Weather in Britain 64ibolya.dr.gottnekne.dr.kunNo ratings yet
- Extraño RelojDocument3 pagesExtraño RelojYina VegaNo ratings yet
- 思想起(音樂比賽版)(總譜及分譜)Document40 pages思想起(音樂比賽版)(總譜及分譜)Liang ZhangNo ratings yet
- 金田弘 (1985.5) 「なかった」考 PDFDocument7 pages金田弘 (1985.5) 「なかった」考 PDFNomura YoshikiNo ratings yet
- Tabla de Referencia A 106 BDocument1 pageTabla de Referencia A 106 BJose Guadalupe DomínguezNo ratings yet
- Article 157718Document33 pagesArticle 157718inourimeriemNo ratings yet
- JR MapDocument1 pageJR Map95pzfmx47nNo ratings yet
- 22 01 2023 Sirvamos Hasta El Fin Esperando Nuestro Galardon PR JavierDocument6 pages22 01 2023 Sirvamos Hasta El Fin Esperando Nuestro Galardon PR JavierhugomartzNo ratings yet
- Seoul Rosenzu 01Document1 pageSeoul Rosenzu 01bxjh9ftqfhNo ratings yet
- Conto Escola Assis 2edDocument10 pagesConto Escola Assis 2edFabricio GuimaraesNo ratings yet
- Topic 3 Ethical and Legal Implications of PracticeDocument7 pagesTopic 3 Ethical and Legal Implications of Practicemarc gorospeNo ratings yet
- TH M His Ar 2015 49Document60 pagesTH M His Ar 2015 49ali ali39No ratings yet
- 19 02 2023 Yo Soy La Puerta PR JavierDocument5 pages19 02 2023 Yo Soy La Puerta PR JavierhugomartzNo ratings yet
- Carnival of Rust PDFDocument4 pagesCarnival of Rust PDFzatanna10No ratings yet
- القمحDocument2 pagesالقمحJOE SAADNo ratings yet
- 11 02 2024 No Busques Nada Fuera de DiosDocument5 pages11 02 2024 No Busques Nada Fuera de DiosJoel Antonio Menendez HernandezNo ratings yet
- PNL y Coaching Ontologico Nivel 1Document66 pagesPNL y Coaching Ontologico Nivel 1ricardoNo ratings yet
- 関西学院大学Document36 pages関西学院大学liq55667No ratings yet
- Reading Practice 2 Japanese StudyDocument6 pagesReading Practice 2 Japanese StudyDavid McCartney100% (1)
- MAML - Volume 5 - Issue 1 - Pages 405-433Document28 pagesMAML - Volume 5 - Issue 1 - Pages 405-433tamershahd06No ratings yet
- 4PM0 01 Que 20150119Document32 pages4PM0 01 Que 20150119munzarinNo ratings yet
- 19 03 2023 Yo Soy La Vid PR Javiier CDocument5 pages19 03 2023 Yo Soy La Vid PR Javiier ChugomartzNo ratings yet
- Vivir Mi Vida Trombone 2 - CompressDocument2 pagesVivir Mi Vida Trombone 2 - CompressSantiago AlbaNo ratings yet
- Wakefield 1Document3 pagesWakefield 1JRaoneNo ratings yet
- Por Que Te Quiero - Bajo Eléctrico (Los Ángeles Negros)Document1 pagePor Que Te Quiero - Bajo Eléctrico (Los Ángeles Negros)Luis FernandoNo ratings yet
- 新美南吉童话中的战争意识Document46 pages新美南吉童话中的战争意识Kai Liang KeeNo ratings yet
- MAML Volume 8 Issue 3 Pages 379-402Document23 pagesMAML Volume 8 Issue 3 Pages 379-402ghadatarek735No ratings yet
- 路線図 v1.21 (201010) JPDocument1 page路線図 v1.21 (201010) JPWazzupWorldNo ratings yet
- Unit 2 T V NGDocument260 pagesUnit 2 T V NGBảo QuốcNo ratings yet
- Kotoba Marugoto 2Document52 pagesKotoba Marugoto 2kikiNo ratings yet
- Kotoba Level N5: 日本語 Romaji Indonesia 動詞 (どうし) Kata KerjaDocument6 pagesKotoba Level N5: 日本語 Romaji Indonesia 動詞 (どうし) Kata Kerjareza fauzanNo ratings yet
- DownDocument90 pagesDownAl aeNo ratings yet